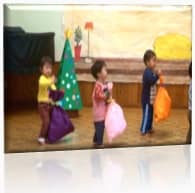音を追求するレッスン
 指先、手首、手のひら、ひじ、脇、肩、背骨、肩甲骨、腹筋、首の傾き、骨盤、膝、足首、踵、つま先・・・
指先、手首、手のひら、ひじ、脇、肩、背骨、肩甲骨、腹筋、首の傾き、骨盤、膝、足首、踵、つま先・・・
ピアノの一音を出すとき、これらすべての部位を意識のコントロール下に置きながら、ピアノから出て来る音の響きに全神経を集中させ感覚を研ぎ澄ませて目指す良い響きの音を聴いていく。
これがツィーグラー奏法の初めの一歩です。
沢山の音が並び、拍子・調性・和声進行・テンポ・フレーズ・対位法的手法・これらを総合した表現内容など…
多くの情報の詰まった曲を弾いていくという事は、気の遠くなるような作業になるわけです。
正に心身の鍛錬あってのなせる業、音楽で人を感動させられるだけの演奏をしていく事は本当に大変な事です。
プロの演奏家である藤原先生のレッスンは、大人のレッスンでなくても僅かなミスも聴き逃されません。
日頃のレッスンで「まあ、このくらいは仕方ないかな」と、つい甘くなってしまっているいい加減さを反省させられます。
暗譜についても、
音のミスは当然ながら、音の長さ、ダイナミクス、ニュアンス、スタッカートetc.・・・楽譜に書かれていることの全てをクリヤにしておかなければ必ず指摘されます。
しかしながら、この寸部の狂いも許されない世界と言うのは、美の追求で、なぜか苦しいことではなく喜びに通じているというのが不思議です。
音楽を楽しむという事で得られる人としての幸福の深さを体験できます。
「ここはどんな感じで弾きたい?どんな様子を表してると思う?」
例えば普通だったら「そよ風が吹いてくるような感じ」くらいの表現になりそうなところも、先生に掛かると・・・
ファンタジーの世界で、自分が主人公になっている。
ドラゴンがいて戦わなくてはいけない状況下。
自分の力では到底負けてしまうが命からがら抵抗を続けている。
地獄の扉の真ん前にいるような血みどろ状態。
そこにペガサスが助けにやって来てくれた!
囁くように「ありがとう」と呟き、やっとの思いでと跨り、そのたてがみにしがみつく自分。
やっと助かったと安堵した後に、空を駆け上がりながら、徐々にまた助けられたことに勇気がみなぎってきて…
自分が、守られていることに気付き「みんなのための頑張ろう!」という気持ちになっていく。
「こんなストーリーを思い浮かべながら弾くとね、聴いている人は引き込まれていくのよ~」と、冗談めかしく。
僅か10小節の間にこれだけのドラマ!!
これを科学的に説明すると・・・
まず弾き手は譜面を理解して弾こうと集中している。
そこに先生がその曲の意向を説明された。
言葉で状況を説明したことで、刺激が弾き手の求心性神経を通って中枢神経に伝達される。
そして遠心性神経を通って脳から抹消器官にシグナルが伝わり、弾き手の志向性が働き、運動系の神経に伝えられて、感覚が動く。それによって演奏が変わる。
話がとても楽しく共感性の高い内容だったので運動と言う反射に直結した、という事なのだそうです。
※参考図書
「耳で考える」-脳は名曲を欲する 養老孟司 久石 譲 角川oneテーマ21
ピアノって、想像するより遥かにアスリートチックなものなのかもしれませんね!
次回のレッスンもビシッといきましょう!!